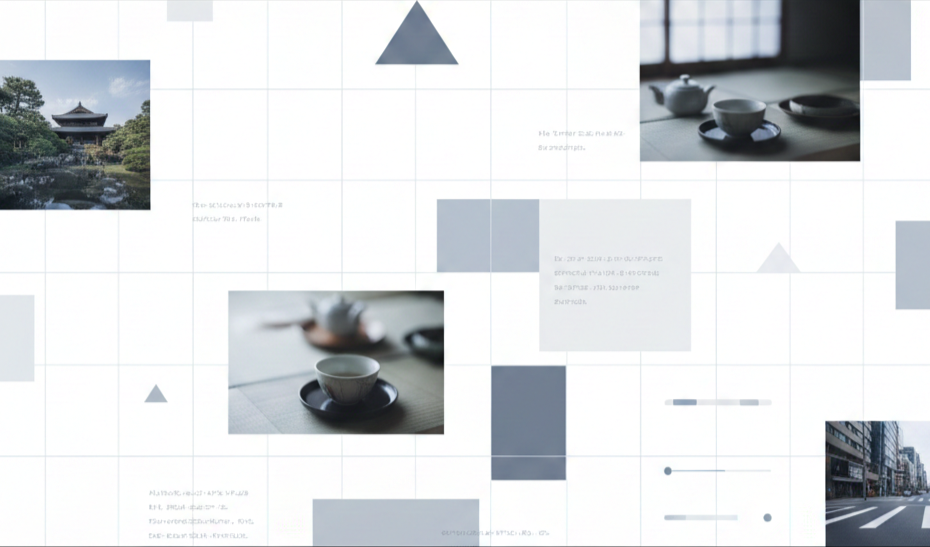Webサイトにおいてスクロールは行為であり、選択です。
にもかかわらず、日本のWebサイトを見ていると「なぜここまでスクロールさせるのか分からない」「これだけ動いたのに、得られる情報が少ない」と感じる場面が多くあります。
本記事では、**スクロール量と情報・体験の“不均衡”**に焦点を当て、日本のWebサイトが抱える構造的な問題と、ブルータリズムがなぜスクロールを“楽しい体験”に変えられるのかを丁寧に言語化していきます。
スクロールが「報われない」と感じる瞬間

ユーザーは、無意識のうちに**「スクロール=対価を得る行為」**として認識しています。しかし日本のWebサイトでは、この前提が崩れているケースが少なくありません。
情報量とスクロール量の不釣り合い
日本のサイトでは、長い余白・一行ずつのテキスト表示・過剰な演出が頻出します。
しかしスクロールして現れるのは、すでに分かっている内容や抽象的な言葉ばかりです。
行為量に対して得られる情報が少ない状態は、ユーザーに徒労感を与えます。
- スクロール量が多い
- だが情報密度が低い
- 新しい発見がない
この三点が重なると、スクロールは「苦行」に変わります。
演出が目的化したWeb設計
本来、演出は情報理解を助けるための手段です。
しかし日本のWebでは、アニメーションやスクロール演出が目的そのものになっている例が多く見られます。
結果として、「動くけど何も残らない」体験が生まれ、ユーザーは離脱します。
日本のWebに蔓延する「スクロール至上主義」
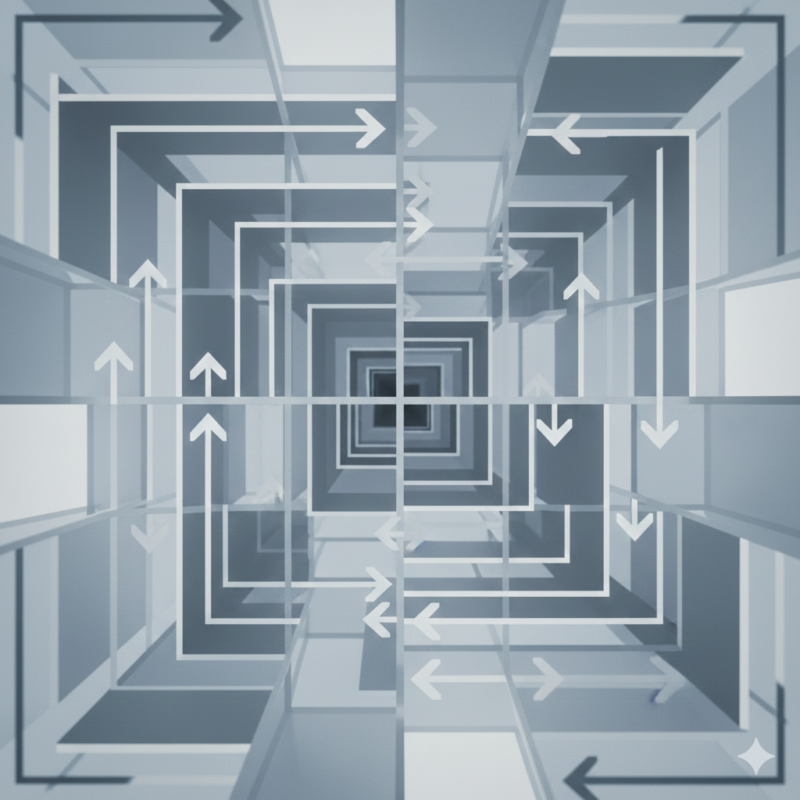
スクロール自体が悪いわけではありません。問題は、スクロールさせる理由が設計されていないことです。
読ませたいのか、見せたいのかが曖昧
日本のWebサイトでは、
**「読ませたい文章」と「雰囲気を見せたい演出」**が混在しがちです。
その結果、ユーザーは次のような混乱を感じます。
- どこが重要なのか分からない
- スクロールの終点が見えない
- 読む覚悟を決められない
これは情報設計の問題であり、ユーザーの集中力を削ります。
「親切」のつもりが主導権の剥奪になる
「順番に見せてあげる」「全部説明してあげる」という設計は、一見親切です。
しかし実際には、ユーザーから選択権を奪う設計になっていることが多いです。
スクロールを強要される感覚は、主導権を奪われた不快感につながります。
ブルータリズムがスクロールを“報酬”に変える理由

一方で、ブルータリズムのWebサイトでは、スクロールが楽しみに変わる瞬間が確かに存在します。
次に何が出るか分からない構造
ブルータリズムでは、秩序をあえて崩す設計が多く見られます。
この「予測不能性」が、スクロールに期待を生みます。
- レイアウトが突然変わる
- 情報の出方が一定でない
- 視覚的ノイズが意図的に置かれている
この不安定さが、「次を見たい」という欲求を生みます。
情報密度と刺激の即時性
ブルータリズムの特徴は、スクロール直後に必ず何かが起きる点です。
テキストでもビジュアルでも、即座に変化が返ってくるため、行為が報われます。
結果として、ユーザーはスクロールを続けます。
スクロール体験は「設計思想」で決まる
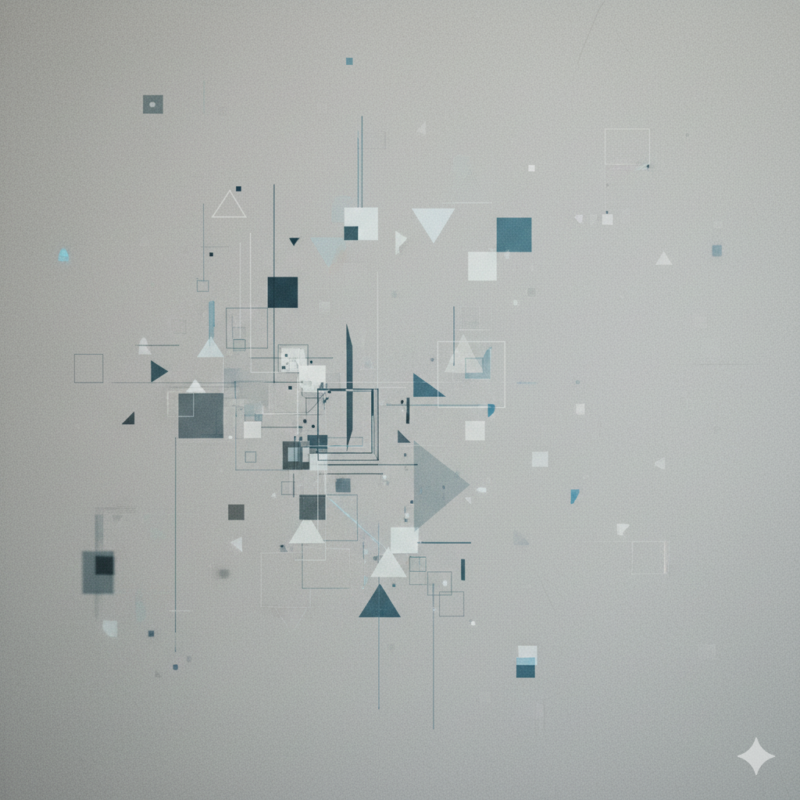
スクロールが報われるかどうかは、テクニックではなく思想の問題です。
スクロールはコストであるという前提
ユーザーの指は疲れます。時間も使います。
つまりスクロールはコストです。
ブルータリズムは、この前提を無視しません。
| 観点 | 日本のWeb | ブルータリズム |
|---|---|---|
| スクロールの扱い | 手段 | 体験 |
| 情報の出し方 | 均一 | 不均一 |
| 報酬の有無 | 薄い | 濃い |
この違いが、体験の質を分けます。
「最後まで見せる」より「次を期待させる」
日本のWebは完結を急ぎすぎる傾向があります。
一方ブルータリズムは、未完・余白・違和感を残します。
その余白こそが、スクロールを続ける動機になります。
離脱されるスクロール、記憶されるスクロール

スクロールは、記憶に残るか、即忘れられるかの分岐点でもあります。
報われないスクロールが生む「無感情」
情報が薄いスクロール体験は、怒りすら生みません。
ただ何も残らないだけです。
この無感情こそが、最も危険な状態です。
ブルータリズムが残す感情の痕跡
ブルータリズムのスクロール体験は、
不快・違和感・驚きといった感情の痕跡を残します。
感情が残れば、サイトは記憶されます。
【まとめ】スクロールが報われる設計とは
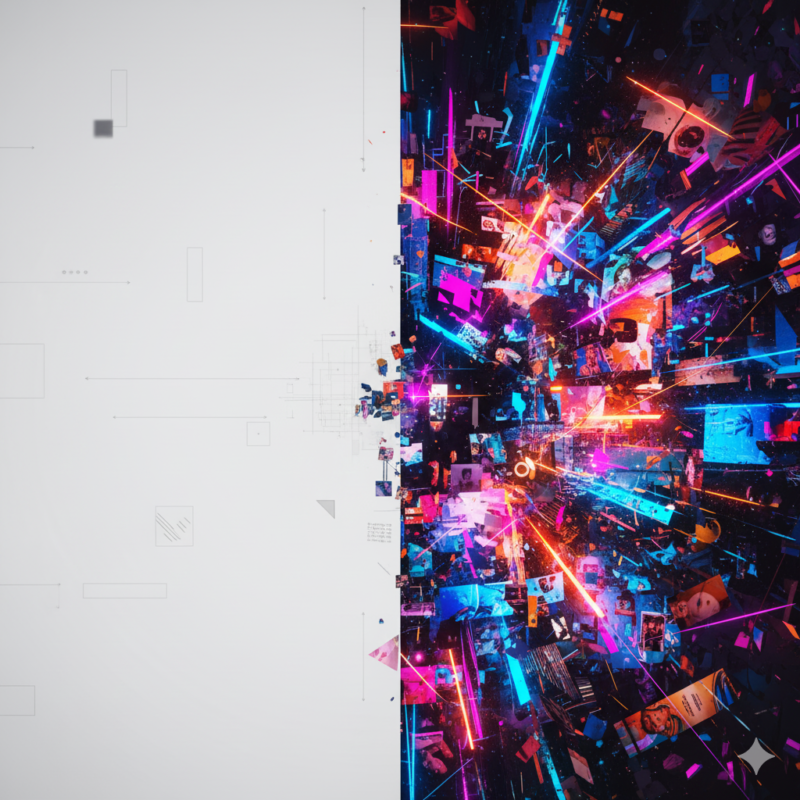
スクロールは単なる操作ではなく、ユーザーが支払う行為コストです。
日本のWebサイトでは、この前提が軽視され、情報と体験の不均衡が離脱を生んでいます。一方ブルータリズムは、スクロール直後に必ず何かを返す設計によって、行為を報酬へと変えています。
スクロールを「させる」のではなく、「したくなる体験」に変えることが、これからのWeb設計に求められています。